■ 肝疾患
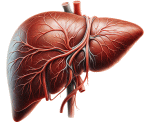
❑ 肝臓は沈黙の臓器として知られており,病態が進行する
まで症状が出ません。したがって,肝臓の病気は、早
期発見が非常に重要とされています。
❑ 2019年のコロナ禍以降は、ステイホームにより食べ過
ぎ飲み過ぎによる体重増加が非常に多くなりました。
過体重やアルコールの過摂取により、脂肪肝や肝障害
が増加しました。
■ アルコール関連肝疾患
◇ 原因と動向



❑ アルコール飲料は,イスラム圏(宗教上の理由)を除
くほぼ全世界で消費されており、安らぎや解放感を
与え、不安や悲しみを慰め、人間関係を構築するの
に役立ちます。
❑ 適正なアルコール摂取量は、日本酒換算1合/日、エ
タノールとして男性は20g以下、女性は10g以下と
されてます。
❑ アルコールは肝臓内で分解され無毒化されますが、大量に飲み続けると
分解が追いつかなくなり、肝臓は障害を受けます。飲酒量が多いと脂肪
が十分に燃焼されず肝臓に脂肪が蓄積し、アルコール関連肝疾患を発症
します。進行すると肝臓が線維化を起こし肝炎となり、肝硬変や劇症化
をおこし、死亡することもあります。
❑ 若年者の飲酒は減少傾向にありますが、多量飲酒者は減っておらず、女性
ではむしろ増加が懸念されています。
❑ 女性の飲酒は、短期間で肝障害が増悪し、ホルモンへの影響、乳がんの
リスク、胎児への影響などが懸念されています。
◇ 病態


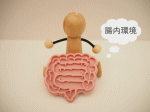
❑ アルコールにより、小腸内細菌の過剰増殖や腸内細菌
叢のバランス変化がおこります。
❑ バクテロイデス門の低下
「善玉菌」とよばれ、動物性たんぱく質や脂質をよく
摂取する人に多く、免疫機能を活性化や炎症を抑制す
る働きが低下します。
❑ フィルミクテス門の増加
「デブ菌」ともよばれ、肥満の一因となる可能性があります。
❑ プロテオバクテリア門の増加
腸内腸管のバリアー機能が破たんし、便秘や下痢など起こしたり、便や
ガスの匂いを悪化させます。
◇ 検 査



❑ 飲酒実態を的確に把握することは困難ですが、飲酒習
慣スクリーニングテスト(alcoholuse
disordersidentification test:AUDIT)により、飲酒
習慣の重症度を推測できます。
❑ 血清γGTP値、平均赤血球容積(葉酸欠乏による大球性
貧血)は、飲酒量の正確な評価は困難です。
❑ %CDTは、アルコールのバイオマーカーとして有用ですが、現在は保険
未収載です。
◇ 治 療



❑ 禁酒と食事療法、減酒薬などの薬物療法、カウンセリ
ングなどの精神療法、 断酒会などへの参加。
❑ 節酒や禁酒、良質なタンパク質摂取、ビタミン・ミネ
ラルの摂取、適正カロリー摂取、 規則正しい食生活。
❑ 禁酒が原則ですが、「減酒・節酒」により、病態進展が阻止することを
目指します「ハームリダクション」も注目されています。詳しくは専門
医におたずねください。
■ B型肝炎
◇ 原 因


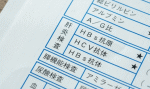
❑ B型肝炎ウイルス(HBV)は、血液や体液を介して感染
します。
❑ 輸血、注射針の使い回し、入れ墨やピアスの穴あけ、性
交渉、B型肝炎に感染している母親から生まれた新生児
への母子感染などで感染します。
◇ 感染経路


❑ 輸血や注射針の使い回し、入れ墨やピアスの穴あけ、感染者からの輸血、
性交渉、C型肝炎に感染している母親から生まれた新生児への母子感染
◇ 治 療


❑ ウイルスを完全に排除するのは難しく、肝硬変や肝がん
に進展しないことを目標とします。
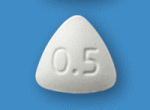
❑ 核酸アナログ製剤による治療は、ウイルスの増殖を抑
制する治療であり、ウイルス体を消滅させるわけでは
ありません。
❑ 肝庇護療法は、肝臓の炎症を抑えることで、肝細胞の再
生を促し肝硬変や肝がんへの進行を抑えます。ウイルス
排除の効果はありません。強力ネオミノファーゲなどが
ー、グリチルリチン製剤、ウルソデオキシコール酸が一
使用されます。
■ C型肝炎
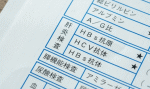
❑ C型肝炎ウイルス(HCV)に感染すると、ゆっくりと病
態が進行し、5~10年かけて次の段階へ進展するとさ
れています。その結果、発ガン率も徐々にに高くなり
ます。
◇ 感染経路


❑ 注射針の使い回し、入れ墨やピアスの穴あけ、感染者からの輸血で感染
します。B型肝炎ウイルスに比し、性交渉や母子感染(C型肝炎に感染し
ている母親から生まれた新生児への感染)は少ないようです。
◇ 治 療



❑ 経口薬で、95%以上の患者さんがC型肝炎ウイルスを
排除できるようになってきました。
❑ 治療が不成功に終わった場合でも、再治療ができるよ
うにもなってきました。
❑ 治療対象外であった非代償性肝硬変の方にもHCVを排
除する治療ができるようになってきました。
❑ 肝がん根治後にHCV陽性になった場合、C型肝炎ウイ
ルスの排除を考慮すべきであると追記されました。
■ 原発性胆汁性胆管炎(PBC)
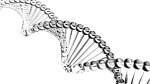
❑ 遺伝的素因を背景くわえ、環境要因がきっかけになっ
ていると考えられています。
❑ 中年以降の女性に多く見られる、肝臓内の細い胆管を
免疫細胞が破壊してしまう疾患です。
❑ 胆管が破壊され胆汁うっ滞が起こり、肝臓内に胆汁が
溜まることで炎症がおこります。炎症が進行すると胆
管消失や線維化が進み、肝硬変や肝不全に進行ことが
あります。
◇ 原 因


❑ 遺伝子多型や陰イオン交換チャネルと病態との関連が報告されています。
❑ 小児期の環境状況(トイレ、道路の舗装状況)、環境中の化学物質への
慢性的な曝露(喫煙経験、染毛剤の使用)の関連が報告されています。
◇ 診 断


| 下記の2項目以上を満たすことが要件 |
|
・慢性に持続する胆道系酵素(ALP,γGTP)上昇,
・抗ミトコンドリア抗体(AMA)陽性,
・特徴的な肝組織所見(慢性非化膿性破壊性胆管炎:CNSDC)
|
◇ 治 療


❑ UDCAが第一選択薬です。
❑ UDCA不応例が20~30%存在し、第二選択薬としてとしてベザフィブラート
が使用されることがあります(保険適応外)。
❑ 治療すれば、予後良好な疾患です。
❑ 診断時にすでに肝硬変まで進行している場合は、治療効果が低く肝不全になり
ます。したがって、早期発見や治療が重要です。
■ 自己免疫性肝炎(AIH)
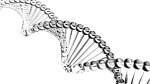
❑ 遺伝的素因を背景くわえ、環境要因がきっかけになっ
ていると考えられています。
❑ 免疫細胞の、量的・質的異常、腸内細菌叢のバランス
が乱れた状態との関連が報告されています。
❑ 特徴的な診断指標はなく、除外診断で確定します。
❑ 原因不明ですが、ウイルスや薬物、妊娠、出産などと
の関連が考えられています。
◇ 症 状


❑ 中年以降の女性に多くみられます。
❑ 健康診断などで、AST・ALT・γ-GTP(ガンマグロブリン)・IgGの
上昇から疑われます。
❑ 慢性に進行しますが、短期間で進行したり、他の自己免疫性疾患を合併
することもあります。
❑ 病気が進行した状態で発見されることもあります。
| 自己免疫性肝炎(AIH)の診断指針2021年 |
|
1.抗核抗体陽性 あるいは 抗平滑筋抗体陽性
2.IgG高値(>基準上限値1.1倍)
3.組織学的にinterface hepatitisや形質細胞浸潤が見られる
4.副腎脂質ステロイドが著効する。
5.他の原因による肝障害が否定される。
典型例 :上記項目で、1~4のうち3項目を認め、5を満たすもの
非典型例:上記項目で、1~4の所見の1項目以上を認め、5を満たすもの
|
◇ 治 療


❑ プレドニゾロンが第一選択薬とされています。
❑ 反応が悪い場合にはアザチオブリンが併用されます(2018年に保険適用)。
❑ 長期予後は一般人口と変わらないとされています。
■ 原発性硬化性胆管炎(PSC)
◇ 病 態


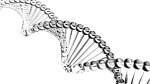
❑ 遺伝的素因を背景くわえ、環境要因がきっかけになっ
ていると考えられています。
❑ 肝内外の胆管に炎症が生じ、その結果、胆管の狭窄や
閉塞を起こします。胆汁の流れがさらに悪化すると、
最終的に肝硬変や肝不全に進展する難治性疾患です。
❑ 肝移植が必要な場合もあります。
❑ AIHとPBCでは両者を併せ持つ場合が、2~19%の頻度
で存在します(オーバーラップ)。
◇ 症 状


❑ 無症状のことが多く、検診で偶然指摘されることがあります。
❑ 炎症性腸疾患の合併している場合は、消化管の症状から発見
されることもあります。
◇ 治 療


❑ 確立した根治療法はありません。
❑ UDCAがPSCに対し第一選択薬で使われますが、長期予後は
良くないとされています。
■ 薬剤性肝障害
❑ 中毒性
 薬品、サプリメントや代謝産物により肝臓が損傷を受 薬品、サプリメントや代謝産物により肝臓が損傷を受
けて炎症が起こります。原因物質の摂取量が多いほど
、障害が強くなります。近年,分子標的薬や免疫チェ
ックポイント阻害薬などの抗がん剤による肝障害が増
加しています。
❑ 体質性
薬物性肝障害の多くが体質性であり、摂取量に関係な
く、体質に依存して起こる障害です。
❑ 危険因子
年齢が18歳以上で肥満、妊娠、医薬品と飲酒の併用、
遺伝子多型などが、薬物性肝障害の発症リスクを増大
させるといわれています。
◇ 治 療


❑ 原因物質である医薬品やサプリメントを中止することで回復します。
❑ 薬物性肝障害スコアリング(RECAM-J 2023)により、薬物性肝障害
診断の可能性を評価します(免疫チェックポイント阻害薬やタモキシ
フェンによる肝障害は対象外になっています。
■ 肝機能全般の検査
| AST・ALT |
・AST/ALT比<1:過食,糖尿病,長期の肝機能障害
・AST/ALT比>1:アルコール,肝炎の急性期,肝硬変,肝癌。
|
| γ-GTP,ALP |
中等度上昇します。 |
| M2BPGi |
肝線維化に特異的で、他疾患で高値になることは稀。
肝線維化の進行と高い相関を持ち、肝硬変から肝癌
への発症予測や肝癌切除術後生存の術前予測にも有用。
|
| FIB-4 index |
検査データ(ALT,AST,血小板数)を用いたスコアであり、
肝線維化の程度を確認できます。 |
| MASLD fibrsis score(MFS) |
年齢,高血糖,BMI,血小板数,アルブミン値,AST/ALT比を組
み合わせて計算し、線維化を評価します。 |
| 血清フェリチン |
MASLD/MASH の30~40%で上昇します。 |
| PNPLA3 |
肝臓細胞の、脂肪を処理する機能において重要な働
きをしており、脂肪性肝疾患の発症や進展に関係し
ていると考えられます。
|
| AUDIT |
飲酒習慣の重症度を評価します。 |
| 薬物性肝障害スコアリング |
薬物性肝障害診断の可能性を評価します |
|